

食を通して見る、社会のあり方と人間の営み(前編)
一人のイギリス人男性が、奥さんと二人の子どもを連れて日本を旅し、各地の日本料理を食べて、驚き、喜び、発見を得る……。そんなストーリーの『英国一家、日本を食べる』(亜紀書房)が発刊されたのが2013年春のこと。13万部を超えるベストセラーとなり、アニメ化されるまでに至ったこの本の書き手が、マイケル・ブースさんです。旅に出て、さまざまな国で実際に暮らしながら、複数のノンフィクション作品を出版し、多数の受賞歴持つブースさんが、最も得意とするフィールドが「食」。自身の肩書きの一つでもある「フードジャーナリスト」とはどのような仕事なのか。ブースさんに伺いました。
profile
-

-
フードジャーナリスト
マイケル・ブース
英国・サセックス生まれ。トラベルジャーナリスト、フードジャーナリスト。著書に『英国一家、日本を食べる』『英国一家、ますます日本を食べる』(以上、亜紀書房)、『英国一家、フランスを食べる』(飛鳥新社)、『英国一家、インドで危機一髪』『限りなく完璧に近い人々──なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?』(以上、KADOKAWA)がある。2010年、「ギルド・オブ・フードライター賞」受賞他、受賞、ノミネート多数。
どうしちゃったんだ、マイケル!食へのスイッチが入ったフランス料理
―― フードジャーナリストになられた経緯を教えてください。
私は大学では英文学や映画、テレビについて学び、卒業後はテレビ番組の制作会社に入りました。でも業界に合わなくて1年で辞めて、その後しばらくタイで暮らしたりした後に、ロンドンの大学院でジャーナリズムを学びました。大学院修了後、フリーランスのジャーナリストとして活動していこうと文章を書き出したのですが、最初から食にこだわっていたわけではありません。
まず始めたのは旅について書くトラベルジャーナリストとしての仕事でしたが、外国に行くと次々に新しい食べものに出会うため、自然と食についても書くようになりました。その後、現在の妻と出会って、彼女の故郷であるデンマークのコペンハーゲンに住むようになったころから、食について書く機会がだんだん増え、いつしかそれが自分の主要なテーマの1つになっていました。


―― 食にはもともと興味があったのでしょうか。
実はそうでもないのです。私は、幼少期はものすごく好き嫌いが多くて、料理が上手な母が美味しいものをたくさん作ってくれるにもかかわらず、一切興味を示さないような子どもでした。ところが8、9歳のころ、突然変化が訪れました。家族旅行でフランスに行ったとき、初日に入ったレストランで、なぜか私はスイッチが入ったように出てきた料理をすべて平らげてしまったのです。ウズラの卵にグリーンピース、ステーキにクレームブリュレ……。家族は唖然として見ていましたよ。「一体どうしちゃったんだ、マイケル!」って顏でね(笑)。
変化が起きた理由は自分でもわかりませんが、いずれにしてもその日を境に私は食の魅力に惹かれるようになって、大学に入学して学生寮で暮らし始めると、なんでも自分で作るようになりました。その後ますます料理にはまり、手の込んだものも自ら作っていくうちに、シェフのようになりたいという気持ちがどんどん大きくなっていったのです。一方、私はものすごく食いしん坊でもあります(笑)。この仕事をやっている一番の動機は、単純に美味しいものを食べたいという気持ちかもしれません。


―― 本を書くようになられたあと、パリの名門料理学校「ル・コルドン・ブルー」に1年間通い、その後はミシュラン三ツ星レストランである「ラトリエ・ドゥ・ジョエル・ロブション」でシェフとして厨房にも立たれています。実際にそこまでやるのはすごいことですよね。
一冊目の本(邦訳『ありのままのアンデルセン ヨーロッパ独り旅を追う』、晶文社刊)を書き終えた後、出版社がもう1冊書かないかと言ってくれたので、そのとき、フランスでシェフになる修行をしてその体験を本にしたいという提案をしました。家族でパリに移住して料理学校に通うなんて夢のような話でしたが、出版社に了承してもらえたので実行に移住しました。つまり、料理を本格的に学びたい気持ちはあったものの、シェフになりたいと思っていたわけではなく、取材という意識が常にありました。しかし結果としては、上位の成績を修め、パリの一流レストランで働くこともでき、本当に貴重な経験をしました。
―― その経験をまとめたのが『英国一家、フランスを食べる』(飛鳥新社)ですね。ル・コルドン・ブルー、そして働いたレストランでは、実際にどのようなことを学び、今どのように生かされていますか?
ル・コルドン・ブルーでは、フランスやヨーロッパの料理を作る上で根幹となる技術をみっちりと学んだのはもちろんのこと、シェフのちょっとした工夫やコツも身につけることができました。例えば、まな板の下に滑り止めとして濡れた紙を敷いておく、といったことです。そして、市場に行けば、買うべき食材を自分で見て判断することができるようになったし、自分で選んだ食材を使い、レシピを見ることなく美味しい料理を作ることができるようになりました。
また、実際にレストランの厳しい調理場に立って働くことで、レストランで出される料理の背後の世界を知ることができました。1つの料理の中にどれだけの技術やエネルギーが注ぎ込まれているか。どういうものがいい料理で、どういうものがよくないのか。現在フードジャーナリストとしてシェフに話を聞くときにも、その経験はとても役に立っているし、文章を書くときの細かな言葉づかいにも、その経験が生かされていることは間違いありません。


ブースさんの著書。右から『英国一家、日本を食べる』(亜紀書房)、『英国一家、フランスを食べる』(飛鳥新社)、『限りなく完璧に近い人々──なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?』(KADOKAWA)
食の背後にある物語を伝えたい
―― フードジャーナリストの役割とはどういったものだとお考えですか?
私は、単純にこのイチゴがすごく美味しいとか、このレストランのスープがおすすめです、と言ったことを伝えたいわけではありません。一番伝えたいのはその背景にあるものです。例えば新しい本の中で、沖縄の海ぶどうについて書きましたが、その主眼は海ぶどうそのものよりも、なぜ沖縄の人が海ぶどうを育て始めたかにあります。それを紐解くことで沖縄の歴史が見えてくるのです。また、九州のアサクサノリについても書きました。高品質のノリが近年育たなくなっているという話ですが、その要因を探っていくと気候変動へとつながります。もちろん、新しいお店を紹介したり、単純に美味しい食べものについて知ってもらうという仕事も必要ですが、私がやりたいことは食の背景にある物語を伝えることであり、それがフードジャーナリストの大切な役割ではないかと考えています。


漬物屋さんにて。漬物の作り方、お店の歴史について取材するブースさん
―― フードジャーナリストとして仕事をする上で重要なことはなんでしょうか?
食であれ何であれ、文章を書く上で何よりも大切なことは、面白いものを書くことです。そのためにはまず、読み手を惹きつける自分なりの文章スタイルを確立することが重要。それができれば、あらゆるテーマについて書くことができるようになるはずです。次に大切なのは好奇心ですね。ふと目にしたことを、「なぜだろう」と思えるかどうか。例えば私は、今もこの部屋の壁にかかっている額の中の漢字の意味が知りたくて仕方ないのですが(笑)、そういう気持ちが私の文章を支えていると思っています。


京都の街並みを撮影するブースさん。好奇心はジャーナリストが持つべき素養の1つと語る
そしてその上で、何か1つの分野に精通すること。フードジャーナリストであれば、例えば豆腐料理については誰にも負けないといった専門分野を持つことです。そのために、自分でも料理をしたり、レストランやバーで働くことができれば実際に経験してみることが大切だと思います。
またそのように、書く以外の仕事をすることは、仕事の幅を広げることにもつながります。フードジャーナリストにはその可能性が広くあります。京都にいて食に詳しければ、旅行ガイドとして錦市場を案内することもできるだろうし、食の問題の専門家として企業のコンサルタントになることもできるかもしれません。


―― フードジャーナリストという仕事の魅力はなんでしょうか?
食を語ることはそのままその国の文化や社会の現状を語ることにもなり得ます。現在の日本人の食生活を見ていると、日本が培ってきた素晴らしい食生活の多くがファストフードに置き換っていて、必ずしもいい方向には向かっていないという印象を受けます。その一方で、そうした流れに必死に抵抗しようとする人たちがいる。私は先日、大分県で有機農業に携わる人たちに話を聞いたのですが、彼らは現状を憂い、なんとか流れを変えようと情熱を持って農業に取り組んでいて、とても心を打たれました。
食を通して社会のあり方や人間の営みが見えてきます。食は誰にとっても身近でありながら、かつ最も奥深いテーマなのです。そこに携わることができるのがフードジャーナリストという仕事の一番の魅力なのではないかと思います。
―― 現在はどのようなテーマに取り組まれているのでしょうか?
日本・中国・韓国の関係についての本を書こうとリサーチを進めています。とても難しいテーマですが、本当に興味深い。もともとはこの3国の自動車産業を切り口に書こうと思っていたのですが、最近は、麺を切り口にする方がよいかもしれないと思い始めています。国同士の関係を描く際にも食は有効な切り口になり得るのです。本当に食は、私たち人間の営みと切り離せないことを改めて感じています。


「人間の歴史は食の歴史だと言っても過言ではない」とブースさん。まさに、食べることは生きることそのものとも言えます。近年、多くの人が食について考え語るようになっていることからも、フードジャーナリストという存在はさらに重要度を増していくはずです。
後編では、ブースさんが見た日本の食文化やフードビジネス、そして今後の世界の食のあり方などについてじっくりと伺います。
他にもこんな記事がよまれています!
-
Interview

2021.01.25
デリバリー特化型「ゴーストレストラン」が支持される理由
株式会社ゴーストレストラン研究所
吉見 悠紀 -
Interview

2017.02.03
IT×漁業で社会を幸せに。 そこには一生をかける価値がある
株式会社フーディソン
山本 徹 -
Book

2022.09.16
バーチャルな世界での、フードビジネスを読み解く
食マネジメント学部
酒井 絢美 -
Interview

2022.06.30
食に磨きをかけ、日本一の食ワールドをめざす阪神百貨店
株式会社阪急阪神百貨店
中尾 康宏 -
Column

2022.01.14
健康のために楽しむバナナミルク ― 日本と韓国の乳食文化
立命館大学食マネジメント学部
マリア ヨトヴァ -
Interview
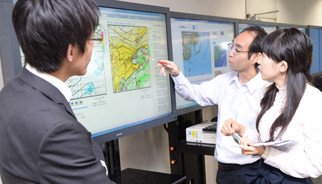
2019.04.15
全産業の1/3が改善!? 日本気象協会が提唱する「食の天気予報」
一般財団法人日本気象協会
中野 俊夫